皆さん、こんにちは。群馬県みどり市を拠点に、公共工事をはじめとする土木工事や解体工事などを手掛けている高草木建設です。
土木施工管理として働く時は、キャリアアップのために「土木施工管理技士」の資格を取得する必要があります。施工管理技士の資格を持っていなければ着任できない役職もあるため、有資格者は多くの企業が求めています。
そんな施工管理技士の技術検定制度が見直され、2024年度から受験資格が緩和されることになりました。そこで今回は、受験資格緩和の背景や具体的な変更点についてわかりやすく解説します。
■施工管理技士の受験資格緩和の背景

施工管理技士の受験資格が緩和される主な理由は、従来の制度のままだと施工管理の担い手が不足すると見込まれているからです。国土交通省の資料によると、建設業の就業者数は55歳以上が約3割、29歳以下が約1割と⾼齢化が進⾏しています。高齢化は日本全体の問題ですが、建設業は他の業界以上に高齢化が加速しているのが実情です。
また、若者の入職者数も大幅に減少しています。2014年度の若年層(24歳以下)の⼊職者数は、ピーク時である1992年度に⽐べて約17万⼈も減少してしまいました。加えて、新規⼊職者の離職率も他の業界に⽐べて⾼く、特に⾼卒者は入職3年以内に半数が離職している状況です。
さらに、施工管理技士の技術検定の受験者数も減少傾向にあります。土木施工管理技士は1
級・2級ともに受験者数が減少し、受験者・合格者の平均年齢は上昇しています。1級合格者の平均年齢を2015年と2005年前後で比較すると、10年間で約3歳上昇(34歳→37歳)しており、20代後半〜30代前半の⼈数が約半数に減少してしまいました。
その影響により、1級⼟⽊施⼯管理技⼠の有資格者だけが就任できる「監理技術者」についても、20代後半~30代後半の若い層の⼈数が⼤幅に減少しています。このままだと、近い将来高齢者が大量離職した時、施工管理が深刻な担い手不足に陥るのは避けられません。
このような状況を改善するためには、施工管理に求める技術力は維持しつつも、資格の早期取得を促進することで、特に若年層に対して「建設業界に在職する動機付け」の強化を行う必要があります。そこで、受験要件の緩和を図ることにより、若年層の受験機会を増やし、有資格者を確保する試みが進められているのです。
■施工管理技士の受験資格はどう変わる?

施工管理技士の受験資格の緩和は、2024年度から実施される予定です。受験資格が緩和されると、具体的にどのような点が変更されるのでしょうか? 制度の現状と改正後の内容を比較してみましょう。
・現状
現状は、受験者の学歴や卒業学科に応じて、受験に必要な実務経験が変化する仕組みです。たとえば、1級土木施工管理技士の検定は、大学の指定学科(土木関連の学科)を卒業した人なら、卒業後3年以上の実務経験があれば受験することができます。指定学科以外の大学を卒業した場合でも、卒業後4.5年以上の実務経験で受験可能です。
一方、高卒者の場合は、指定学科を卒業したとしても卒業後10年、指定学科以外の卒業だと11.5年以上の実務経験が求められます。先に2級を取得しておけば、2級取得から5年以上の実務経験で第二次検定を受験できますが、大卒者に比べて取得に時間がかかる点は変わりません。
また、指定学科の⾼卒者は、指定学科以外の⼤卒者よりも1級を受験できる年齢が遅いなど、不自然な「逆転現象」が生じている箇所もあります(2級を取得せずに1級を受験する場合)。このように現行制度は、学歴等と受験要件のバランスが必ずしも取れていないのです。
・改正後
2024年度からの制度改正後は、受験に必要な実務経験の年数が学歴によらず統一されます。まず、1級の第一次検定(学科試験)は、19歳以上であれば誰でも受験できるようになりました。2級の第一次検定は現行制度と変わらず、17歳以上なら誰でも受験可能です。2021年度に実施済みの制度改正により、第一次検定の合格者は「施工管理技士補」の資格を取得できます。
そして第二次検定(実地試験)は、1級および2級技士補としての実務経験が一定以上あれば、誰でも受験できるようになりました。2級は必要な実務経験が3年で固定され、1級は担当した工事の規模によって1年~5年の間で変動します。一定規模以上の工事の実務経験であれば3年以上、監理技術者補佐としての経験であれば1年以上で第二次検定を受験できます。
つまり、学歴が一切問われなくなり、年齢と第一次検定合格後の実務経験だけが要件となったのです。単純計算だと、最短20歳で1級施工管理技士の資格を取得できることになります。大卒でも高卒でも、もちろん中卒でも条件に違いはありません。純粋に受験者の実力が問われるようになったのに加え、受験に必要な実務経験が大幅に短縮されたことで、改正後は受験者の増加が期待されます。
なお、2028年度までは、制度改正前の受験資格に基づいて第二次検定を受験することができます。自分にとって都合のいい条件を選んで受験するといいでしょう。
■指定学科を卒業するメリットはなくなるの?
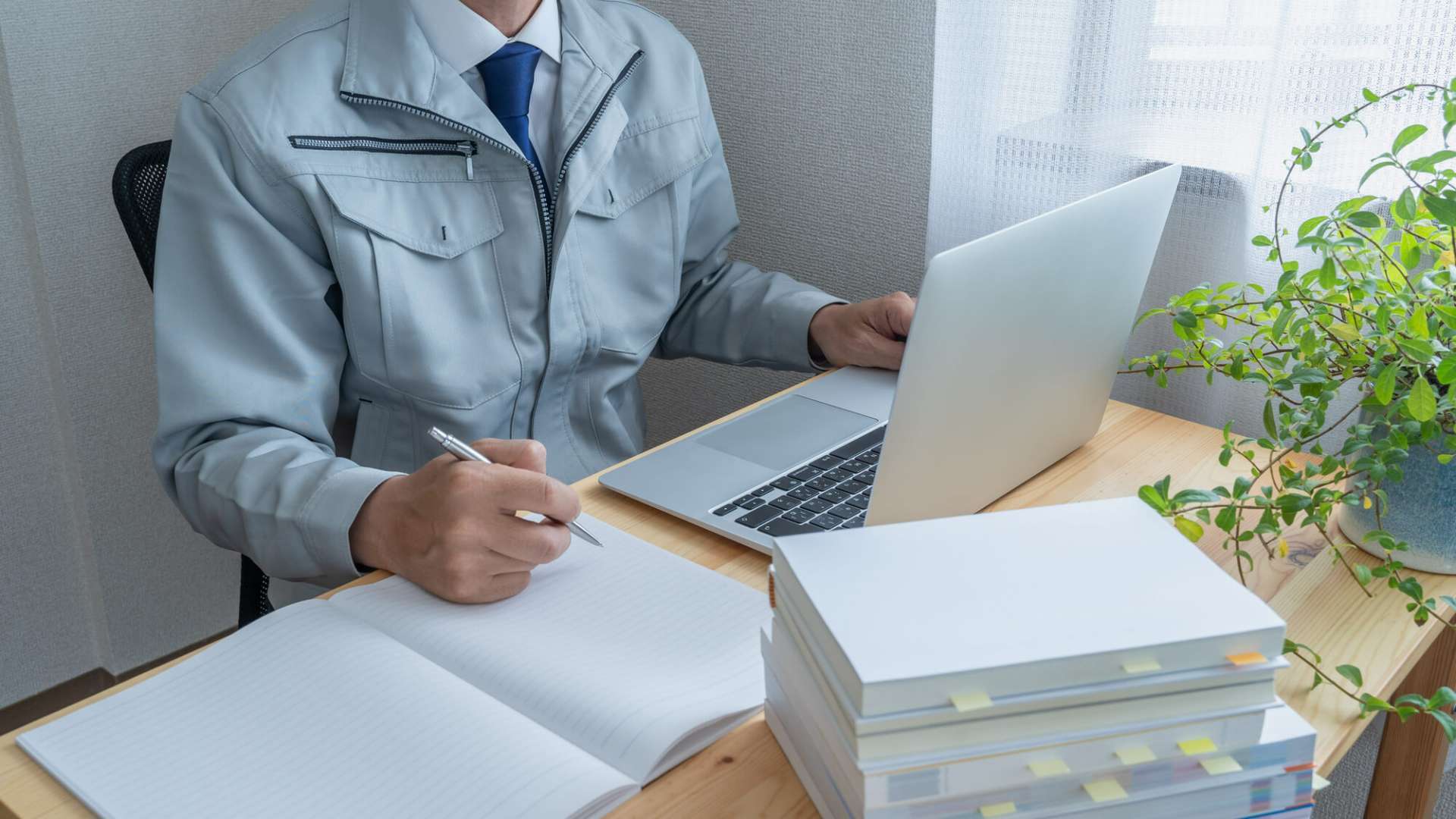
施工管理技士の受験資格が緩和されると、学歴に関係なく実務経験のみを基準に受験できるようになります。こう聞くと「指定学科(土木や建築の専門学科)を卒業するメリットがなくなってしまうのでは?」と不安になる方もいるでしょう。実際のところはどうなのでしょうか?
結論からいうと、指定学科を卒業するメリットは改正後も残ります。特定の学科を卒業すると、第一次検定(学科試験)において一部の科目が免除されるからです。たとえば、大学で土木工学を専攻した人は、土木施工管理技士の第一次検定のうち、工学基礎に関する問題を解く必要がなくなります。
また、受験のことを除いたとしても、学校で学んだ専門的な知識は、施工管理になってから大いに役立ちます。したがって、改正後も指定学科を卒業する意味は十分あるといえるでしょう。なお、従来制度との整合性や公平性の観点から、免除制度は2029年度以降に開始される予定です。
■高草木建設では、土木施工管理技士を募集しています!

施工管理技士の受験資格緩和の背景には、建設業界の深刻な人手不足や高齢化といった問題があります。受験資格が緩和されることで若年層が受験しやすくなれば、有資格者が増加し人手不足の解消につながるでしょう。
もちろん、当面は施工管理の「売り手市場」が続くと思われます。今の時点で施工管理技士の資格(特に1級)を持っている方は引く手あまたなので、機会があればより条件のいい会社に転職してみてはいかがでしょうか。
高草木建設は、群馬県みどり市を拠点に公共工事や戸建ての新築・リフォームを行っている会社です。建築工事も手掛けていますが、土木工事をメインに受注したいと考えており、そのために土木施工管理技士の資格をお持ちの方を募集しています。
弊社は公共工事をメインに行っているので、仕事の量が安定しており、規模の大きい現場を経験できます。そのため、安定した収入を得たい方や、スケールの大きな工事にチャレンジしたい方におすすめです。
また、福利厚生が充実しており、残業も月に20時間程度と働きやすい環境が整っています。個人のがんばりを正当に評価する社風なので、努力した分だけ昇給・昇進することが可能です。
その他、土木作業員や重機オペレーターも募集しています。これらの仕事に興味のある方、そして専門資格をお持ちの経験者の方、高草木建設で働いてみませんか? まずはお気軽にご連絡ください。皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしております!


